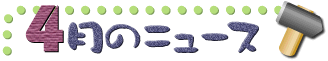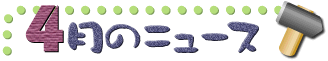|
上げた利益を職人にも還元せよ
第44回大手建設住宅企業交渉 |
手間アップ前向き検討
大和ハウス確認書もかわす |
| 全建総連関東地方協議会は4月13日、14日の両日、のべ1480人(東京土建443人)の参加で、第44回大手建設・住宅企業交渉を行ないました。(交渉の主な内容は4〜5面) |
 |
| 建設・住宅企業決起集会(豊島公会堂) |
ゼネコン28社、住宅企業12社、サブコン5社に対して実施した今回の交渉はアスベスト問題、耐震偽装事件、官製談合事件など一連の建設産業の信頼を失墜させたことに大手企業の社会的責任をただし、法令遵守を貫かせること、また急激に上昇している収益を還元させ、低賃金・低単価構造の打破と現場環境改善を迫ることが主なテーマでした。
賃金問題では企業側が現場労働者を調査した結果があまりにも低いことから、「ためこんだ利益を出せ」と語気鋭くやりあう企業がいくつもありました。そういった中でも、住宅業界2位の大和ハウス工業では、大工手間一日2千円上げるよう積算基準など改定するようにとの組合側の要求に対し、「引き上げを前向きに検討したい」との回答をしました。また旭化成ホームズと鹿島建設では、「調査結果は上昇傾向にある」との回答があり、鹿島の担当者は「職人不足により腕のいい職人の奪いあいになっていることが背景にあるだろう」とコメントしていました。
技能工不足はどの企業でも「深刻だ」と危機意識を持っており、技能と品質に連動した賃金・労働条件の向上、技能工養成費用等の下請への支給制度実現を迫っていくことが今後の課題になってきます。
建退共の普及については鹿島建設と竹中工務店が、この春あらためて官・民の全現場に貼付適用現場であることを周知するよう、所長と監督に通知したとのことです。
「石綿労災認定」への協力も約束
アスベスト職業病認定の協力では、今回新たに4社が「施工証明」の発行などを約束し、これでほぼすべての交渉企業が認めました。
いくつか前進的な成果を得た今回の交渉ですが、これらの回答については次回(10月)までに現場から検証をすることと、賃金については引上げの大衆的運動をさらに強めていくことが大切です。
確認書は大和ハウスが「不払い根絶」「建退共普及」「アスベスト粉塵対策」「労働安全徹底」の4セット、大豊建設は昨年秋の「不払い」にひきつづき他の3つを、旭化成とエスバイエルは「労働安全」と「建退共」について取り交わしました。 |
| 許せない不払い解決への誠意みせぬ元請 |
交渉に先だち豊島公会堂で決起集会を開き、鈴木絋関東地方協議会議長は「要求は13項目に渡るが、一つでも二つでも成果をかちとれるようにがんばろう」と参加者を激励しました。
佐藤正明全建総連書記長は「ゼネコンは売上げも、利益も上げている。大手はコスト削減で生き残れるが、私たちは生き残れない。今日、明日の取りくみに期待します」とあいさつ。
現場からの報告でAさんは「三次が倒産し元請に立替払いを請求したが、一次に対応をまかせるだけで誠実な対応がない。元請は何の被害も受けず工事代金を受けとっているのに、なぜ私たちが被害を受けなければならないのか。安心して働ける建設業界にしていこう」と訴えました。
宮本英典東京都連書記次長が要求項目の説明を行ない、交渉団ごとに打合わせをして各交渉企業(ゼネコン・サブコン28社、住宅企業11社)に向かいました。 |
|
| 春の拡大月間スタート |
| みんな行動に参加しよう |
 |
| TBSのナイター放送で東京土建加入のCMが秋まで流れます |
東京土建は4月27日から5月30日まで、「春の拡大月間」にとりくみます。全支部が「月間目標3・5%、年間到達6%」達成をめざして奮闘します。
本部では未加入事業所への「けんせつ」特別号送付、テレマーケッティングを行ないましたが、これまで以上の好反応です。
さらに今年はTBSのラジオ「エキサイトベースボール」を毎週木曜日提供し、東京土建の名を広くアピールします。
本人・家族入院医療費全額払い戻しの「土建国保」、充実した保障の「どけん共済」、仕事に欠かせない「石綿(アスベスト)作業主任者講習」をはじめとする資格取得など、東京土建の魅力を未加入者に伝え、組合をさらに強く大きくしましょう。 |
|
港が50周年を祝う
50年在籍組合員を表彰 |
 |
| めでたく鏡割りを行ないました |
【港・書記・村松高広記】
4月16日、結成50周年式典・祝賀会を高輪プリンスホテルで開催。来賓は本部木下中央執行委員長をはじめ56人、組合員・家族96人が参加。式典では、在籍50年となる永年在籍者の表彰もおこなわれました。
林一男委員長は1956年4月に中央支部が港支部に改称してからの50年を回顧。そして50周年記念事業としてかかげた新会館建設、分会再編・事業所分会設立、最高現勢で50周年をむかえる目標を達成させたことに確信をもち、前進する決意を表明しました。
前進座の太鼓と演舞が祝賀会を盛り上げたあと、北川静夫副委員長の閉会あいさつで春、秋の拡大運動の成功も誓い合いました。 |
|
| 公契約求める意見書つぎつぎ |
江東は「二者懇」が力に
区を動かし現場聞きとり |
 |
| 桜井國之さん |
【江東・土木・桜井國之記】
江東支部が03年8月に、184人の参加で成功させた個人請願行動から3年7ヵ月たった3月30日、江東区議会で『公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保等(公契約法)を国に求める意見書』が採択されました。
具体的行動は区議会全会派要請と議員懇談、傍聴行動や対区交渉を粘り強くおこない、地元建設業協会との継続的な二者懇談会で賛同を広め、地域共闘でも学習活動を大いに展開しました。
さらに大きな力となったのが区発注工事現場での調査・分析活動です。建築・土木の契約実態をすべて分析、また区にアポイントをとらせ現場に入り労働者からの聞き取りや現場所長との懇談をもとに、理事者、議員に説得力のある資料を提供できたことなどです。
また何といっても最大の要因は組合の組織を増勢させた数の力を発揮したことです。
意見書採択は公契約運動のスタートです。今後は、『公契約法を推進する自治体』との立場を区に認識させた上で、その立場でやらなければならないことをあらためて提案し、条例制定にむけての布石を打つこと。仲間に対しても組織前進が要求実現の大きな力になることを大いにアピールしていきたいと思います。 |
新宿区議会も採択
切実に訴え議員動かす |
【新宿・大工・林博八記】
「公契約条例(法)の制定を国は速やかに実施すること」を求める意見書は3月24日、新宿区議会で採択されました。東京23区では10番目となります。
今、国や自治体の公共・委託事業は人件費を無視したダンピング受注やピンハネが横行し、最低賃金法違反や賃金不払いまで常態化しています。
新宿支部が、地元建設事業所訪問の要求資料をたずさえて、初めて陳情書を提出したのは4年前でした。区議会議員の中には「公契約って何?」というような状況でした。
支部では区議会・総務区民委員会で公契約条例の学習会や懇談会を数回開いていただきました。懇談会に参加した仲間から「賃金の下落が続き、このままでは後継者のなり手が出てこない」といった切実な訴えが次々と出されて、議員さんの心を動かしたのだと思います。
4年間の長きにわたる努力が実を結んで、可決されたときは大きな喜び、この成果を確信に、支部産業対策運動の第一歩にして、仲間の要求実現をめざしてがんばります。 |
|
5月1日 メーデーに参加を
出し物コンクールも実施 |
 |
| 昨年の最優秀賞作品 |
第77回中央メーデーは5月1日、代々木公園で開かれます。三多摩メーデーは井の頭公園で開催します。
「メーデー」の起源は、1日10時間もの過酷な労働をしいられた労働者たちによる労働時間短縮をめざすたたかいに端を発します。1886年5月1日、8時間労働を求めた約30万人の労働者が米国全土でゼネストを実施し、経営者に労働時間の短縮を約束させました。
その後、経営者側はヘイ・マーケット事件を利用し労働組合を弾圧。しかし8時間労働を求めるたたかいは全国に広がり、1890年5月1日、各国の労働者が第1回国際メーデーに立ち上がりました。
今年のメーデーは、小泉「構造改革」がもたらした格差の広がりや、憲法改正をねらった国民投票法が計画されるなど国民生活の危機と日本国憲法の危機がせまっている中でおこなわれます。青年部などが作る「出し物コンクール」に期待します。 |
|
| 中央執行委員会06年度任部分担 |
4月1日の第1回中央執行委員会で次のように新執行部の任務分担が決定しました。
(対外的な任務は省略)
委員長
木下勝三郎
副委員長
野部安重(国保組合理事長、主婦の会担当、統制委員長)
池上武雄(産業対策、事業所対策、学習制度化委員長)
木暮龍彦(技術研修センター理事長、後継者対策担当)
棗田敏正(書記局給与規程改定委員長・収益事業対策)
市瀬正樹(どけん共済会理事長、綱領改訂委員長・規約改正委員長)
書記長
告坂真二
書記次長
清水謙一(産業対策事務局長)
梅沢仁(国保組合専務理事)
松本秀典(社保・税対・教宣・主婦の会担当)
井手口行夫(組織・財政・厚文、総務、どけん共済会)
《専門部の分担》
社会保障対策部
部長・大内貞雄常任中執、松尾慎一郎担当常任中執、担当中執・小島保二、本田幸一、玉利照明、石垣雅之、和田光太郎
仕事対策部
部長・瀬田宗市常任中執、松井民人常任中執、担当中執・瀧澤正徳、大塚重吉、須藤春夫、岡田豊志、山極武久
賃金対策部
部長・宮田清志常任中執、白滝誠常任中執、担当中執・片平正夫、斉藤栄一、橋本昇、北川誠太郎
労働対策部
部長・高木史雄常任中執、三宅一也常任中執、担当中執・柴田良憲、鈴木昭義、伊藤文夫、川島環
技術対策委員会
部長・柄澤文雄常任中執、松森陽一常任中執待遇、担当中執・岩佐俊光、橋本英夫、西野弘、小原英治
後継者対策部
部長・佐藤豊常任中執、大田隆樹青年部長、寺川慎二常任中執、担当中執・佐藤康治、巻田幸正、蓬澤幸一、田中健青年部書記長、岩田輝幸
税金対策部
部長・小沼正和常任中執、大内良雄常任中執、担当中執・鈴木英雄、小出康雄、山岸郭志、坂本秀夫
厚生文化部
部長・清水正彦常任中執、高木典男常任中執待遇、担当中執・井上敏雄、浜崎和馬、野辺秀男、根釜勝
組織部
部長・市瀬正樹副委員長、不破幸司常任中執、担当中執・野澤國男、田中茂、作田信義、加藤行夫、三木勉
教育宣伝部
部長・小倉一男常任中執、向井光也常任中執、担当中執・豊田佳二、高橋勲、菅原節雄、市川秀夫
財政部
部長・棗田敏正副委員長、石井章二常任中執、担当中執・林一男、吉野弘司、大田克徳、倉林広幸 |
|
| 「はなみずき会」春の交流会 |
 |
| あいさつする井上会長 |
府中国立の本間さん、台東の石渡さんは酸素チューブをつけて参加。4月9日、東京土建会館で「はなみずき会」(じん肺・呼吸器疾患患者と家族の会)の春の交流会が開かれ、来賓の海老原医師も含めて59人が参加しました。
井上会長は「最近労災の認定までの期間が早くなったが特Aランク(緊急に検査の必要な人)の288人は1日も早く専門医で検診を受けてもらいたい。労災申請中の人もこれから大いに励ましあっていきましょう」とあいさつ。
海老原医師が記念講演をしました。調布の八鍬さんは「皆さんのお顔を見て、元気をいただきました」。
交流会のあと「アスベスト被害者の全面的補償を求めるアピール」を確認。次回の再会を約束して散会しました。 |
|
春の拡大月間 がんばる分会長
組合の良いところを話して |
拡大月間やりぬく決意 みんなでやれば楽しい
年間目標をやりぬくため行動大きく |
 |
| 内藤さん |
春の拡大月間がはじまります。東京土建本部では21日に「春の拡大出陣式」をおこない目標達成への意志統一をしました。「けんせつ」では『がんばる分会長』を紹介します。各ブロックから分会長の「拡大月間をやりぬく決意」を紹介します。
対象者には根気よく
【世田谷・喜多見分会長・内藤政一さん】
分会では、支部の拡大統一行動日に合わせ15群に割り当て、群役員と分会役員で組合員を訪問。そこで組合員に対象者をあげてもらい、当日あるいは後日に役員が対応するようにしています。この情報が拡大の基礎で、最も重要なことだと思います。もらった対象者には根気よく接し、組合のよいところを話してあげることが大事なことではないでしょうか。 |
 |
| 都築さん |
先進に学び独自企画も
【府中国立・国立北分会長・都築功さん】
そうですねェ、すすんでいる支部、分会をマネしたことでしょうか、それと本部からくるパンフの内容で、できそうなことにチャレンジしています。組織の強化、活動家を増やす、新しい企画に飛びついてみる、独自の学習会を企画する、こんなものですね。総会、拡大、住宅デー、レクについては準備会や推進委員会をおこない、充分な準備をして実践する。そして楽しみな反省会をおこなうことです。 |
 |
| 阿久津さん |
拡大はいつも波乱万丈
【葛飾・奥戸分会長・阿久津正さん】
奥戸分会は500人から470人を上下して支部をイラつかせています。34群中、企業群が13群あり、他の群にも企業グループはそれ以上ありますが、仲間を拡大する中でこうなったわけです。拡大月間はいつも波乱万丈で、いっこうに進まないかと思えば、今春みたいに10人を一気に拡大。みんなでやれば楽しいもの。地域工作教室も予約が4件、そのうちに仕事につながるのではとがんばっています。 |
 |
| 唐沢さん |
「春一番」は毎夜の訪問
【狛江支部・駒井町分会長・唐沢明寿さん】
私は分会長として五年目になります。狛江支部では今年初めて春一番拡大行動をしました。参加者が少なく大変ですが、毎夜組合員の家をまわりました。土建ファミリーカードなど説明をしながら、加入をお願いして歩きました。目標6人のところ、打上げまでに4人加入しました。町場の対象者が少ない分、企業関係者に声をかけ、残りの分を5月の拡大で達成できるようにがんばりたいと思います。 |
 |
| 高田さん |
仲間と一緒にがんばる
【墨田・墨田分会長・高田玲子さん】
墨田支部で女性の分会長は初めてのことで、大きなプレッシャーを感じています。墨田分会は最も大きい分会です。そんな大きな組織の先頭になって組合活動を引っ張っていけるかどうか二重の不安です。しかし所属の役員や組合員、書記の皆さんからの協力を得て、一緒に頑張っていきます。そして加入している組合員さんが「東京土建に入っていてよかった」と思われるような活動を進めていきたい。 |
 |
| 堀内さん |
活発な仲間は私の誇り
【西東京・第六分会長・堀内均さん】
私は、分会総会において組織部兼任副分会長から、分会長に選任されました。分会では再編成で合流した仲間が活発で喜ばしい結果となっています。これは再編成前から17年間も、春と秋の拡大運動に平行して、日帰りと一泊の旅行をかかさず続け、仲間どうしの協力と和をつくり、あらゆる運動の推進力となっています。
私はその先頭に立って活動できることを誇りに、がんばるつもりです。 |
 |
| 石川さん |
36人「今年もやるぞ」
【北・北東分会長・石川義勝さん】
「今年もやるぞ」と顔をあわせるや否やの第一声、しつこいほどのねばりで拡大成果を上げてきた。昭和33年に15歳で赤羽の畳屋さんに小僧として入り、独立。昭和57年につきあいのある大工さんに勧められ組合加入。入った時にそのまま群会計にされて以来、分会役員を続けてきた。「あれから俺は組合狂いになった」と。昨年33人の目標をやり切り、今年は目標36人。 |
 |
| 米村さん |
役員団結してとりくむ
【多摩稲城・多摩第一分会長・米村正樹さん】
初めて分会長を引き受けました。昨年は分会書記長をやりましたが、分会長が決まらず一年がすぎました。しかし、担当オルグの役員と分会会計で力をあわせて秋の拡大月間も目標を達成し、少しずつ協力者も出てきました。今年は分会四役も決まり、春一番から分会のたて直しにとりくんでいます。新役員一致団結して拡大や分会活動にがんばります。 |
 |
| 櫻井さん |
一致団結してがんばる
【品川・南品川分会長・櫻井守さん】
「笑顔が絶えない分会ですよね」と書記からいわれますが、たしかにウチの分会は、お酒が好きな人が多く、にぎやかでいい分会だと思います(笑)。おかげさまで、去年は秋と年間の拡大目標を達成することができました。春の拡大も、一致団結してがんばると共に、若い人たちを訪問する時には「もうひと声」をかけて、「組合に出てみようかな」と少しでも考えてもらえるようにしたいと思います。 |
| 青年部、主婦の会も一丸で奮闘 |
 |
| 田中さん |
【本部・青年部書記長・田中健さん】
青年部では、「支部青年部に結集する仲間づくり」を重点にした方針を大会で確認しています。春の拡大月間は、その第一歩として、行動に参加する仲間、新しい仲間をふやし、青年部への結集をすすめていきたい。また、後継者対策部と一体となった分会青年部の連絡員選出の課題も、全都の青年部が一丸となってとりくみ、大きく前進させていきます。 |
 |
| 藤本さん |
【本部・主婦の会組織部長・藤本冨美江さん】
04年より40周年に向けて、会員拡大を20%増の2万4000人めざしてきました。いよいよ総仕上げの年、2月の総会では3000人の拡大目標をやりきる意志統一をしました。春の拡大月間では、昨年の成果1250人以上の会員拡大ができる気合を各支部からもびしびしと感じています。
全支部の力を結集して40周年を迎えたいと思います。 |
|
賃金いま上げないでいつ上げる!
第44回建設・住宅企業交渉 |
ゼネコンは月50万以上の支払いを
残業代なし長時間労働の住宅企業 |
企業への主な要求
(1)耐震偽装や官製談合など企業の社会的責任が問われています。貴社の見解は。
(2)現場の賃金実態を調査し、(何次の、何職の、何歳か、発注単価は)賃金の引上げを。
(3)公共、民間を問わず、設計労務単価(関東で平均17、860円)以上の支払いを。
(4)生活に必要な賃金として月額50万円(日額25000円)以上の支払いを。
(5)1日8時間労働の適正な工期の設定。時間外労働には残業代の支払いを。
(6)工事契約は着手前に最終下請業者を含めて文書で。法定福利費は別枠支給を。
(7)後継者を育成できる単価を。
(8)不払い発生時の立替え払い。
(9)トイレ、手洗い、休憩所の設置、熱中症対策など。
(10)アスベスト対策の徹底。
(11)労働安全衛生法の遵守、労災かくしの根絶。
(12)建設業退職金共済制度の加入促進。 |
 |
| 大林組は「300万なければ生活できないのですか」と発言した |
大林組
下請への指導強める
「労務費の手形払いは相談を」
【本部・白滝誠記】
市瀬正樹団長による「仕事不足の町場の方が賃金は高い。大儲けしている大ゼネコンは率先して利益を還元すべきだ」との追及に、「技能レベルも生活スタイルもいろいろある。みんなが月50万円取ることが妥当なのか。本当に年間300万では生活できないのですか」と、私たちの切実な要求を逆なでする大川第一工事部長の答弁に交渉団は怒りをあらわにしました。
大林組の姿勢は現在の格差社会、競争万能、自助努力第一の小泉・竹中流経済路線をそのまま肯定するかのような、冷たく具体性のない回答が支配的でした。
交渉団が「低賃金で若者が離職している。この状況をどうとらえるのか」「後継者不足は大企業の社会的な責任と捉えるべき」と迫ったところ、「一次下請の会合でも同様の発言は多く、このままでよいとは思っていない。まだ解決策は見えないが、検討したい」と、多少なりとも変化を見せました。
二次下請が労務費込みの150日もの長期手形の不渡りを出して倒産した事件に関して、元請の指導責任を追及した場面では「指導は機会あるごとにしているがむずかしい問題」だと逃げ腰でした。これに対し交渉団は、「下請と労働者への契約や支払い状況を定期的に点検するなど未然の防止策をとっているゼネコンもある。元請責任を貫くこと」を強く要求しました。企業側は「点検については即答できないが、指導は強める。労務費の手形払いはすぐに相談してほしい」との答弁がありました。 |
 |
| 鹿島の賃金は昨年より上昇した |
鹿島
月収34万、年収410万
「50万は理解できるし必要」
防衛施設庁発注工事での談合事件や耐震偽装、アスベスト問題などで鹿島の社会的責任と再発防止対策を求めたのに対し、回答はむなしさを感じさせるものでした。
鹿島との交渉は佐藤良治団長(千葉土建)、木下勝三郎副団長(東京土建)を先頭に総勢33人が参加して行ないました。
会社側からは、安藤聡東京本社安全環境部部長はじめ14人が出席し、回答は安藤部長と近井玉樹東京支店安全環境部次長(企業交渉窓口担当者)が中心となって行ないました。
現場の賃金実態調査では、50現場、2400件のサンプル調査の結果から、東京・千葉では「底を打った感」があり、要望にある月収50万円は「理解できるし、4人家族では必要」としながら、月収調査で34・2万円、年収410万円と回答しました。
前回調査では月収32・9万円、年収400万だったとして「上向きな気配が感じられる」とのべました。
これは、首都圏での工事量の増加と一部に職人のとりあいも見られるという状況を反映したものですが、交渉団は空前の利益を上げているゼネコンは現場労働者にそれを還元すべきであり、また低賃金の原因を現場労働者の責任といわんばかりの「労働者の選択制・流動性」を口にする企業側の態度を「安けりゃやめればよいというのはビッグにあぐらをかいた言い草だ。われわれは仕事をしなけりゃ食えない。技能者なしに建設はありえない。もっと現場労働者を大事に、人間らしく扱え」と迫りました。 |
前田建設工業
作業証明を拒否
健診費用も単価に含む
【本部・中宿稔記】
アスベスト作業証明書の発行はしないという数少ないゼネコンの前田建設工業に対して、法令遵守、賃金、証明書発行などを中心に交渉。窓口である宮澤安全労務グループ専任部長ら7人が対応しました。
「企業として信頼・信用の確保は必要。社会的ルールは守る。社内には昨年からワーキンググループをつくり、本格的に推進している」と回答するが、アスベストの作業証明書は「就労場所・労働者の出入りが激しく特定できない。行政からの指導では対応するが、直接証明はしない」。
アスベスト健診費用負担では「労働者の直接の雇用主が負担するべき。費用については材工共の契約なので含まれていると考えている」と、企業の社会的責任を放棄する回答。交渉団からほとんどの企業が証明を約束していることを伝えると共に健診の費用負担を求める発言があいつぎ、前田建設から「他の状況も確認し、2カ月後には証明できるかどうか回答したい」と秋の交渉前に回答することを約束させました。賃金問題では、「昨年から積算の金額は変わっていない」との回答に、昨年秋と比べ、平均の賃金は変わらないものの、最高・最低の金額が下がっていると追及し、労働者に適切な賃金が支払われるように下請への指導を求め、検討するとの回答を引き出すことができました。 |
 |
| 熊谷組は重層下請が賃下げにならないように検討すると回答 |
熊谷は下請を指導せよ
設計労務単価よりなぜ低い
【本部・澤田高志記】
熊谷組とは、宮田清志団長他32人で交渉。冒頭熊谷組より、数年間にわたる企業再建に区切りがついたと発言があった。企業の社会的責任については、コンプライアンスプログラムによって社内通報制度を実施していると説明。
施工の品質は前進しているが、一方で労働災害の被災者が年間15人であり、前年度の2・5倍になっていることから今後労働安全に力をいれていくという説明があった。
現場の賃金調査については、工事の端境期のためにサンプルが少ないということだったが、発表された一日の賃金額はどの職種も設計労務単価より低いので、交渉団は「なぜ設計労務単価より低いのか」説明を求めた。
回答は、労務費はすべて現金で支払っている。設計労務単価より低いのは、一次下請以下は重層下請のために下回っているのではないかというものであった。
組合側としては、下請段階で設計労務単価を下回らないようにするために、熊谷組が責任をもって協力会社に文書で指導することを求めたが、「何らかの措置を考えたい」という回答が出された。
組合側は次回10月の交渉時に、現場労働者の賃金・単価を引き上げる具体策を示してもらうことを要望し、岸土木部長から検討させてほしいと回答があった。
その他に、アスベスト被害、労働者派遣法、賃金・工事代金の不払い対策等で交渉をすすめた。後継者育成については、「企業として必要不可欠なこと」と回答があったが、そのための費用は専門工事業者の責任とするものだったので、組合側は元請企業がもつものだと指摘をした。 |
飛鳥建設
賃金要求は国交省へと
【本部・溜口芳明記】
冒頭、団長の野部副委員長から今回の交渉の趣旨について説明。
飛島建設は企業の社会的責任については、「マニュアル作りにとりくんでいる。ダンピング競争は建設業法18条違反を引き起こすので避けたい」と回答しました。
賃金実態調査を135人からアンケート形式で公共11、民間18現場の調査結果について報告がありました。
その他の要望に対する回答では、「1次業者との請負契約であり2次、3次のことはわかりかねる。労務費だけをとりだした議論はできない」など企業責任を回避する発言に終始しました。
賃金引き上げ要求には、「国交省に組合から要求してほしい」。「大手のダンピング受注には不安を感じる」など、誠意ある回答になりませんでした。
駐車料金負担の要求に、「重層下請が解消されれば別だが」とはぐらかし、「産廃処理費の負担はやめてほしい」との要望には、「それはそうですね」などと回答しました。
交渉団の「正確に回答を求める」との追及に、現場で解決できなかったことは「本社安全環境部に連絡いただければ解決する」との回答を得て時間切れで交渉を終えました。 |
 |
| 銭高組は賃金調査結果をプリント配布してくれました |
銭高組
10時間以上働いているぞ
「調査もっと進める」
【本部・唐澤一喜記】
銭高組は、現場の賃金調査した46作業所についてプリントで公表しました。仲間からは、「サンプルが少ない。何次の職人かわからない。作業時間も平均8時間はありえない」と迫り、銭高は元請社員による聞き取りのため不十分な点を認め「次回はもう少し突っこんだ調査をする」と答弁。
賃金問題では、「常用としては、設計労務単価を上回っている。逆に他のゼネコンの単価を教えてほしい」と答弁があり、交渉団からは「一次ではなく、現場の労働者のことをいっている。他社と比較するのではなく、御社の考えを聞いている。重層下請をなくしてほしい。バブル期以上の仕事を受注している中で賃金引上げは今しかない」と再度押し返しました。
「業界全体で底上げができればよいのだが…。重層下請問題は、今後とりくんでいきたい」。36条協定の届出については「届出がないことはない。適正な単価を払っている。残業代の支払いも各下請の事業主さんが支払っていると思う」とあいまいな答えでした。
仲間からは「10時間以上仕事している仲間が多くいる。元請として何とかならないのか。36条協定の実態・事実関係をつぶさに調べてほしい」と要請しました。
錢高は建退共の現場説明会を快く開催してくれたこと。賃金調査をプリント配布したこと。不払いでも月初めに職人の賃金が払われているか調査している点などについて、これからも続けてほしいと交渉団からさらなる対応強化を求めました。 |
住友林業
平均賃金2万1515円
「施行証明は協力します」
【本部・鈴木康弘記】
住友林業住宅本部との交渉を池袋のコアいけぶくろで行ないました。組合側は木暮龍彦副委員長を団長に30人の仲間が参加。住林側は小林哲也住宅本部首都圏生産管理センター長他3人が応対しました。
まず住林側から要望書への回答がありました。前回交渉の際組合側の要望もあって賃金調査のサンプル数が2倍以上になり、大工など7職種の平均賃金が1日あたり21、515円(就労時間は8時間25分)、平均就労日数は月24日と回答。しかしこれは協力業者から無記名アンケート方式で集約されたもので、「一日8時間25、000円、月額50万円以上の賃金確保を」という要求に対しては「特定建設業者としての責任は認識しているが、現場労働者と直接雇用関係にないので約束できない」と前回同様の答えをくり返すにとどまっています。
アスベスト対策では「労災認定のための、過去の工事についての施工証明書の交付」要求に対し、賃金の回答と同じように「直接雇用関係にないので」と逃げる住林側に、他企業との交渉では施工証明書交付を約束させている事実を説明し、「協力する」と約束させる成果をあげることができました。
終了後、「実際に住林の現場で働く仲間に参加してもらうとか、事前に多くの住林現場データを集めてのぞむことが交渉をすすめるカギだ」という発言がありました。 |
三井ホーム
「平均46万3千円」
8時間労働で再調査を
【本部・中村修一記】
三井ホームとの交渉は、新宿野村ビル会議室で実施。池上武雄副委員長を団長に33人の仲間が参加。三井ホーム側からは、宮下尚之技術統括本部工事推進グループ責任者ほか2人が応対。大工職(80人サンプル)の月平均賃金の報告があり、40歳代で50万6千円、40歳代で45万5千円、平均46万3千円が示されました。
組合側は「1日8時間就労としての賃金を明確にし、残業代などを含めない」金額を報告するように求め、次回までに再度調査を行なうことが確認されました。
アスベスト問題について、三井ホーム側からは「現在の建材には含有されておらず安全である」の回答に対し、「過去においてアスベストが含有されていたのは偽わらざる事実であり、アスベスト含有建材の使用期間に就労した仲間の救済に元請としてどのような対応をとるのか」とせまりました。
これに対し三井ホーム側から「就労している職人は当社の雇用契約及び賃金台帳に照らしても労働者そのものであり、その労災申請に対しては力添えをしたい」との回答を引き出しました。 |
 |
| 賃金の回答を拒否したSXL |
SXL
建退共と労働安全
2つの確認書取りかわす
【本部・上野聖治記】
エスバイエルとの交渉には、清水正彦団長(本部厚生文化部長)以下37人が参加しました。エスバイエルからは、鈴東部生産推進部長など4人が対応しました。
まず、「実働8時間、週40時間労働」の点では、「当社は直接常用工を採用していない。すべて請負なので、できるだけ週40時間になるよう努力している」とあいまいな答弁。時間あたりの換算でも、「3100円」と、昨年秋の答弁をくりかえすだけでした。
「一次への発注単価」についても、「メーカーごとに工法、単価が違う。誤解を招くので、公表はさし控えたい」と前回同様、逃げの答弁に終始しました。
「アスベスト被害者の労災適用」については、「当社の現場で罹患したことが明確になれば、すべて適用する」と答弁。ただ、「施工証明書」の発行については、「注文書を発行しているので、それで代替できるものと考えている」とのべ、基本的には発行しない考えを表明しました。
交渉団は秋の交渉までに「施工証明書」を発行する方向で再検討するよう要請しました。
「建退共の加入促進説明会」については、「協力業者の集まりで説明しているので、全建総連の説明会は特に考えていない。ポスターの掲示も控えたい」とのべるにとどまりました。
交渉の成果としては、「建退共」「労働安全」の二つの確認書を取りかわしました。交渉団は、あとの二つの確認書もかわすよう求めましたが、今後の検討課題となりました。 |
|
黒田さん 61歳の建築カレッジ卒業
高校教師から大工へ |
定年まで待てない ものづくりへの強い衝動で
高齢者の住宅改修したい |
| 都立高校で物理を教えて30年、黒田順さん(東村山支部)は定年前の59歳の時に「大工になりたい」と退職し、カレッジで2年間学びました。「高齢者からここ直して、と頼まれて、ハイ、ハイと、そんな大工になりたいですね」と黒田さんは明るく笑います。 |
 |
| 平行弦トラスを活用した木の梁を考案しました |
‐‐定年まであと1年、なぜ教師をやめて大工になろうとしたのですか。
黒田さん 定年後の教員は、65歳まで働ける嘱託の道か、趣味の世界に入ってろうそくの火が消えるようになるかですが、僕は社会から引退したくない、何か身につけて、もう一回社会人になりたいと思ったのです。
物理で30年間飯を食ってきたけど、ものづくりは大好きだった。とにかくものをつくりたいという衝動があって、大工の基礎から学びたいと思っていたのです。
たまたま僕の住んでいた大家さんが東村山支部副委員長の広田隆雄さんで、広田さんからカレッジを紹介してもらいました。
基礎をおぼえるのに5年かかるといわれ、定年を待っていられないと思いきって59歳で退職し、カレッジに入学しました。
 |
| 2年間学んだ成果を卒業制作で発表しました |
カレッジの卒業制作
軸組工法にトラスを融合
‐‐カレッジで学んだものは。卒業制作は木造軸組で間取りが変更可能なハイブリッド構造住宅に挑戦しましたね。
黒田さん カレッジでは、家一軒すべてに関することを教えてもらうわけですから大変な勉強をさせてもらったと思います。夢のような2年間で、あっという間にすぎた感じでした。
技能は体でおぼえるもので、僕の場合なぜだろうと考えちゃうから、そこで体がとまっちゃう。やっぱりなれですね。
高齢者の住宅改修ができるようになりたい、というのが入学動機で、介護の大変さもわかっているつもりです。
卒業制作では、日本の住宅は構造部が間取り優先で、家族構成がかわると耐用年数があるのにこわしてしまう。なんとか住宅の延命ができないかと考え、軸組工法にトラスを融合させ、大空間を保証し、自由に間取りを変更できるようにした。
80年育った木で100年住めるようにすれば、森林資源の保護にもなると木製ラチス梁を制作しました。
もう少し修行して
弱者のために働きたい
‐‐カレッジを無事卒業しいま61歳。いつごろご自分の看板を上げるのですか。
黒田さん もう少し修業しないとダメです。構造計算と積算見積りもきちんとできるようになりたい。総合力がないとダメですね。昔の教員仲間から少し注文がくるようになったのですが、まだ半人前です。
弱い者いじめのご時世です。お金のない人は修繕をやりたくても頼めない。なんとか弱者のために働きたい、と思っています。 |
| カレッジ生の卒業制作作品 |
 |
 |
 |
金額時 三層目の研究
漆ぬり、金パクにも挑む |
住宅の増改築
日々の仕事に直結する研究 |
神輿
一人ひとりの長所を活し参加できる組織づくり |
|
|
新宿
満開の桜見物 柴又から里見公園へ散策 |
 |
| 柴又帝釈天に勢ぞろい |
【新宿・大工・深沢浩記】
花に誘われ、仲間が集まりました。新宿支部は4月9日、柴又から里見八犬伝で有名な桜の名所、里見公園までの小さな旅を25人の参加で行ないました。
駅前広場のフーテンの寅さんのブロンズ像に見送られ、帝釈天に向かいます。参道にはお店がずらりと並び、仲間たちもお土産の草団子やくず餅買いに忙しく、次は柴又街道を横切り、矢切の渡しに向かいました。
渡し舟に乗り、対岸の市川市まで十分間の短い船旅も楽しいひと時。天気もよく、江戸川堤を里見公園まで1時間ほど散策、里見公園では桜の木の下にシートを広げ車座になり、お弁当を広げ満開の桜を肴に会話もはずみます。
帰りは桜並木を通って矢切駅で解散、楽しい一日をすごしました。 |
|
| 前進座の5月公演 |
中村梅之助の「魚屋宗五郎」
名作「謎帯一寸徳兵衛」 |
前進座は今年5月22日に創立75周年を迎えます。今年の5月公演は記念公演にふさわしく中村梅之助の「口上」と前進座創立に初演され72年ぶりの上演となる南北サスペンス狂言の傑作「謎帯一寸徳兵衛(なぞのおびちょっととくべえ)」と中村梅之助の「魚屋宗五郎(さかなやそうごろう)」です。
会場 三宅坂・国立劇場
とき 5月21日(日)
開演4時30分
料金 7200円
締切 4月27日 支部事務所
 |
| 清水さん |
【厚生文化部長・清水正彦】
創立75周年の節目に前進座の歴史とかかわりの深い二作品が上演されます。
「謎帯」は幻の名作ですし、また梅之助きわめつきの宗五郎に会えます。創立の伝統を、今の第三世代といわれる俳優たちがみごとに受け継いだ舞台を見せてくれると思います。みなさん、国立劇場でお会いしましょう。
杉並は共済学習会後に観劇
【杉並・書記・双木敦志記】
杉並支部では、毎年5月の前進座公演にあわせて、新しく厚生文化部長になった人を対象に昼は共済学習会を行ない、終了後に参加者を中心に観劇しています。
支部から1000円の補助があるので、かなり参加しやすい観劇料になります。(分会でも補助を行なっているところもあります)中村梅之助の口上もあるので楽しみです。 |
|
| 映画 |
| 1リットルの涙 |
【練馬・タイル・掛端光夫記】
世の中にこんな病気があったのか。健康だった娘が病に侵され、障害を持ち、やがて命の灯火が消えてゆく。懸命に支える家族、友達の姿、何よりも自分の病を知ってから自立し生き続けようとする主人公の姿に感動は大きかった。4月15日練馬公民館で、上映された「一リットルの涙」に久々に涙を流した。区内の山彦作業所が障害者自立法を広め運営費捻出の一環にとりくみ、4回の上映で約600人、土建からは150人が参加し大きな感動を共有した。
先にテレビでの放映を見ていた娘たちと、家に帰ってから話が弾んだこともよかった。 |
|
練馬住宅デー
1群1企画で飛躍 |
参加者なんと5割増
子ども対策も一工夫して |
【練馬支部仕事対策部】
練馬支部は昨年、住宅デーを「1分会複数会場開催」から、「1分会1会場開催に力を集中」、「仲間の出番を増やす」「1群1企画」の方針へと発展させました。
この結果、81%の群が企画を作り、参加率も上昇し昨年秋の参加を5割以上上回る1212人の組合員、家族が参加しました。また、多くの分会で「はじめてみる組合員がいた。若い人も出てきた」という声もあがりました。
耐震の問題では、区防災課の協力で起震車体験コーナー(石神井台分会)、家具転倒防止金具の取り付け実演(早宮分会)など8分会が実演企画を行ないました。来場者も増え、住宅相談も過去最高の39件を受けました。
はじめて区教育委員会の後援を受けたこともあり、協力してくれた学校も増えました。仲間の協力で小学校のPTA会長と一緒に学校を訪問、「たこ焼き・焼きそば・お菓子つかみ取り」を打ち出した独自チラシを学習塾、野球教室に配る(土支田分会)という経験も生まれました。
工作教室も全分会が実施し、「ふだん子どもと一緒に工作することがないので大変よかった」など好評でした。
綿菓子を子どもは無料とし、アンケートに回答してもらい礼状を出して次回につなげる(高松分会)、「今までの会場では対応できないので、会場を変える検討をする」(南田中分会)、「会場レイアウトの検討やテント、企画を増やす計画」(石神井台分会、桜台分会)など、練馬支部では今年の住宅デーに向けた検討を始めています。 |
|
| リフォーム受注対応が大切です |
住宅リフォーム推進協議会と野村総合研究所が実施したリフォームした経験のある人を対象に「施工者をきめた理由」のアンケート調査では次の順になっています。
野村総合研究所
(1)対応のていねいさ 34%
(2)友人などの推薦 27%
(3)価格の安さ 24%
(4)ニーズの的確な把握 20%
(5)ヒアリングと提案のていねいさ 19%
(6)担当者の人柄 19%
(7)価格の明朗さ 18%
住宅リフォーム推進協議会
(1)会社の信用・知名度 48%
(2)担当者の対応・人柄 22%
(3)工事の質・技術 20%
(4)信頼できる人の紹介 16%
「契約した会社を何で知ったか」では「以前に工事を依頼した」が33%でトップ。 |